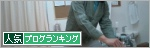https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid02B4RZQmJZYu8cds8Q5rPNGizx6h1zR3GEeNMoDE9VR7JdwtPV7GHWtYK34Nv8z9xNl
日本は車移動を余儀なくする患者に対し、何なら目の前まで車で乗り付けた患者に対し、また、車移動が見込まれる時間帯にも血中に薬物が残存する服薬指導をしているにも関わらず、或いは翌朝まで余裕で持ち越す事が想定される患者に対し、一言くらいの注意は添えても、運転禁止薬物を渡しています。
念の為ですが、当該禁止薬物はあくまで車の運転のみではなく、一例として添付文書の記載を丸々書き写せば、
>>自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう
と範囲は広く、実際はいわゆる車に限った話でもありません。ただ大概は、引き続き運転禁止薬物を服薬しながら車を運転をしていると想定されますが、飲酒運転幇助と同等の行為が平然と店先で日々行われている一方で、何か起きた時のペナルティは全て患者が被るバランスの悪さがあります。
>>薬物の影響で正常に運転ができないことをわかっていながら運転した時点で、過労運転等という交通違反にあたります。さらに、事故を起こした場合、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります※1)
>>実際、2022年には、前日に睡眠薬を飲んで運転して事故を起こし、1名を死亡、3名に重傷を負わせた男が懲役7年の刑に処されました※1)
飲酒運転も事故を起こした時に初めてバレるように、当該薬物の服薬による運転も事故を起こした時にしかバレないかもしれませんが、薬物は飲酒と異なり呼気では分かりませんので、仮に事故を起こしたとしても、単純な処理で済んでいる事例も相当数存在すると想定されます。
その為、以下に挙げる被疑薬一覧に並ぶ数字も、極々僅かなものと考えられますし、個人的にこのような事故と呼ばれる事後的な状況のみならず、当該薬物達の反応による煽り運転、或いは煽られるような非円滑な運転(のろのろ、蛇行その他)にも、大きく薬物は影響していると考えています。
以下は近年のまとめ※2)になるようですが、「被疑薬 交通事故」で調べれば、異なる年で類似したまとめも確認出来ます。※2)を参考に、分かり易いよう先発品の商品名に順序はそのままで上から書き換えていきますが、
-----
リリカ 運転禁止薬
マイスリー 運転禁止薬
ビ・シフロール 運転禁止薬
チャンピックス 運転禁止薬
トラムセット 運転禁止薬
リタリン/コンサータ 運転禁止薬
ドグマチール 運転禁止薬
ハルシオン 運転禁止薬
コロナウイルスRNAワクチン 不明
レンドルミン 運転禁止薬
セロクエル 運転禁止薬
デパス 運転禁止薬
サイレース 運転禁止薬
ジプレキサ 運転禁止薬
レキップ 運転禁止薬
エクア 運転注意薬
パキシル 運転注意薬
ミカルディス 運転注意薬
ソラナックス 運転禁止薬

-----
次に参考として、攻撃性の惹起をリスクに持つ薬物を記載します。数値が高いほど、そのリスクは高いと理解して問題ないと思います。
Chantix(Varenicline)(チャンピックス)18.0
Prozac(fluoxetine)(プロザック)10.9
Paxil(paroxetine)(パキシル)10.3
Amphetamines(アンフェタミン)9.6
Strattera(atomoxetine)(ストラテラ)9.0
Halcion(triazolam)(ハルシオン)8.7
Luvox(fluvoxamine)(ルボックス、デプロメール)8.4
Effexor(venlafaxine)(エフェフサー)8.3
Pristiq(desvenlafaxine)(プリスティーク)7.9
Zoloft(sertraline)(ジェイゾロフト)6.7
Ambien(zolpidem)(マイスリー)6.7
Lexapro(escitalopram)(レクサプロ)5.0
Celexa(citalopam)(セレクサ)4.3
Abilify(aripiprazole)(エビリファイ)4.2
Amitriptirine(トリプタノール)4.2
OxyContin(oxycodone)(オキシコンチン)4.1
Wellbutrin/Zyban(bupropion)(ブプロピオン)3.9
Geodon(ziprasidone)(ジオドン)3.8
Ritalin/Concerta(methylphenidate)(リタリン、コンサータ)3.6
Trazodone(トラゾドン)3.5
Remeron(mirtazapine)(リフレックス、レメロン)3.4
Neurontin(gabapentin)(ガバペン)3.3
Keppra(levetiracetam)(イーケプラ)3.3
Valium(diazepam)(セルシン、ホリゾン、ジアゼパム)3.1
Xanaz(alprazolam)(ソラナックス、コンスタン)3.0
Cymbalta(duloxetine)(サインバルタ)2.8
Klonopin(clonazepam)(リボトリール、ランドセン)2.8
Risperdal(risperidone)(リスパダール、リスペリドン)2.2
Seroquel(quetiapine)(セロクエル)2.0
Lamotorigine(ラミクタール)0.8
Valproicacid(デパケン、バレリン)0.8
Phenytoin(アレビアチン)0.4
Carbamazepine(テグレトール、テレスミン)0.3
Paliperidone(インヴェガ)0.7
Clozapine(クロザリル)0.6
Lorazepam(ワイパックス、ロラゼパム)0.3
-----
また前項の通り、向精神作用物質の特徴は
>>自殺念慮、自殺企図、敵意、攻撃性等の精神症状の発現リスク
が全般的に見込まれます。小難しい事はさて置き、このような状態で車を運転したらどうなるかを考えると、流石に危ないものですが、以前も挙げたように「養命酒だから良いだろ」と、朝から駆け付け3杯飲んで車を運転している人も居るのも事実です。
この問題は「先ず避けられない」を前提に考えたほうが賢いと思います。こちらが歩行者で、向こうが養命酒を飲んで酔っ払って突っ込んでくる可能性もある為、それらのリスク回避の対策を打つ事が先でしょう。
幾らダメと言っても無駄なものは存在すると知り、それで解決しているのなら、既にどこかの誰かが解決させているか、或いは誰もが自制で何とかなる問題であれば、そもそも問題化しない問題と知る事も大切かもしれません。
※1)https://news.yahoo.co.jp/articles/b17de85c72c4ec0c415affd5bca9426320450be4
※2)https://smart-flash.jp/sociopolitics/283407/image/1/?rf=2
参考)https://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/departments/establishment/pharmaceutical/files/55735.pdf
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid0P138NFHp4XoBqhpCDaewnJTk3DMDFJgmRxi6MjJ8BBKiJP8pJ1EJeag5whpGj4p8l
ボールペンや鉛筆、スマホやPC等、思考を視覚化する道具は幾つか存在しますが、文章を考えて書く時に、同じ文章を書こうとしても、それぞれの道具でどことなく変化が生まれる理由に、ゴーっと頭に流れている文章を、如何に素早く文字として安定的に落とし込み続けられるか否かが、変化の理由と捉えています。
例えば、筆先がグラングランでインクも切れ気味のボールペンと、筆先がカチッとして安定的にインクが出続けてくれるボールペンでは、前者の道具そのものの不安定要素に気を取られ、書く気力が失せてしまうと思います。
それでも無理に書こうとすると、グラングランやカスカスインクのストレスで、どこか文章も乱暴になったり、適当に端折ってしまったり、丁寧さが失われる傾向があり、それは後に自分自身に跳ね返ってくる可能性があります。
このように、傍目には同じボールペンでも、道具次第で変化が生まれる事には薄々気が付いていましたが、それは直接的に文字化させる道具となるボールペンや鉛筆、スマホやPCだけではなく、その文章を書く人間が座る椅子や机ひとつ取ってもそうなのかもしれないと気が付きます。
-----
腰を破壊する椅子の存在とその理由に気が付いてから、受傷の再現性を確認する為に、足を組む、座る時間を変える、机に腕を載せて体重を分散させる等の条件を足したり引いたりしながら数か月に渡って様子を見ているのですが、その過程で別途気が付いた事に、椅子に座る必要がある時は、何かの用事を椅子に座って行う必要があるから、となります。
椅子に座る事が目的なのではなく、用事を済ませる事が目的な訳で、その目的を済ませる為には椅子に座る必要がある、です。その中で椅子と腰の関係性にリソースを割かれていたら、椅子に座って行う用事に差し障る事になります。
また、もしかしたら用事に夢中になっていると、座っている最中のリアルタイムでの負担と、蓄積による後の破壊にその段階では気が付けないリスクを抱え、それがいずれ何気ない拍子に急激な痛みへと発展します。
その再現性を数か月に渡って確認しているのですが、先述の通り椅子に限った話でもなさそうで、何かの用事を足す為に必要とする道具そのもののストレスに曝されながら行う用事は、用事そのものに影響を与えかねない事に気が付くものです。
それぞれで環境は異なると思うので、それぞれで合う合わないは異なるのかもしれませんが、よく「良いものを使え」と古くから言われる理由がそれと関連するのかもしれないと、遅まきながら考えるものです。
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid02LE4vUXRfKpnpxHyyeuaDE2P62xEF5qhqcEpAEpV1SW6RGAB2DHPHzZWcQbYzJWQ3l
神経を切断して見ると、中心部に近くなるほど栄養血管が到達していない事が分かります。罹患細胞の回復(それを意図的に反映させる人為的なメディエータ惹起の話題は過去参照)や維持は血液で賄われていますが、先述の通り中心部の栄養血管は乏しく、その逆に表層部ほど豊富に存在します。
当該細胞は血管を豊富に持つ表層部から、自律的/経時的に治り始める特徴を示します。良い面、良い見方をすれば、早期的な回復は透過性が高い状態の継続が早期に抑止され、普段なら通過しない分子量の物質の侵入を最小限に抑える効果があります。
悪い面、悪い見方をすれば、受傷部位が深い中心部まで到達していた場合、中心部の回復を待たずに表層部だけ閉じる可能性です。そうなると当該神経は受傷前と比較すれば、異常な状態で落ち着いて居座り続けるリスクが見込まれます。これらを招く行為は、物理的、或いは薬物でも示唆され、慢性化の懸念材料になります。
今は病期が急性期ではなく慢性期である事を前提とします。患部そのものは当該栄養因子の生合成は既に乏しく、自律的に生成されても当該栄養因子の分子量は大きい為、透過性の低下した当該病期では入り込む隙間がない状態がネックです。
ここまでを慢性化のひとつの理由とした場合、「ではそこにアプローチすれば良いのでは?」となりますが、ひとつのネックは先述の通り、また、当該栄養因子の産生は、体性神経の場合、後根神経節や前角細胞が見込まれています。
>>BNBはBBBに準ずる機能性が示唆されるなか、異なる点は神経根と自由神経終末で一旦連続性が絶たれている点です。この解剖的な脆弱部位を逆手に取ります。また、前者近傍に存在する各部位は、知覚神経であれば後根神経節、運動神経であれば前角細胞が、蛋白合成を育む重要部位と示唆され、当該部位近傍まで届け、カスケード化させたinflammationを意図的/人為的に誘導して得られる結果も多い※1)
先日も触れましたが、後根神経節は高い機能性を持つ一方、代償としてか高い有窓性を持ち、物質の侵入も許し易く、壊れ易い側面もあります。
>>例として後根神経節を取り上げても、頸椎や胸椎、腰椎でも脆弱度は異なり、自律神経節も同様に脆弱、また、腓骨神経も物理的な圧迫なく優位に傷害されるのも興味深いですが、当該部位達の受傷は、ビタミンB6の過剰摂取や糖尿病、ワクチンでも惹起されるギランバレーのような感染症先行型含む自己免疫疾患諸々、抗がん剤等の薬物、精神的ストレス、後に帯状疱疹と呼称される事になるウイルスの潜伏感染部位等、多岐に渡り※2)
しかし動物は上手く出来ているもので、外部からの物理的なエネルギーに対しては容易に到達出来ないよう、横突起や肋骨突起、椎間孔が壁となって守ってくれています。
勿論、壁そのものが物理的なエネルギーで壊れ、それが原因で受傷する事例もありますが、引き続き大雑把に進めると、容易に到達出来る構造ではない部位を賦活化させる必要性、当該メディエータを惹起させる必要性、左記2点を相殺させない取り組みの必要性が生まれます。
ここまでが末梢を受傷した場合となりますが、この観点でシェア内の中枢が受傷した場合の取り組み方も見ると、末梢よりも更に手の届かない部位の傷害だとしても、どこで栄養因子を生合成させれば生理的に運んでくれるかも、並行して考えられるようになります。
※1)https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/7476441565780378
※2)https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/7427707560653779
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid0KxTCCmQ3zxUi1aKJvyJtAidshMC7qWCXWY5uU6M1GfGW6L7RGo9VBwjiprp6XRjsl
https://news.yahoo.co.jp/articles/84d680d18bc50dd78fb04a6d62ac463612b4384e
こちら※1)も見てきたものの、その内容が具体的に書かれていないので分かりませんが、雰囲気的に幹細胞培養上清液(+エクソソーム)等を取り扱う方々の事を主に指しているのでしょうか。
厚労省承認という表現は一旦置き、従来の幹細胞培養液ではなく幹細胞培養”上清”液とは、幹細胞を培養した際に生まれる文字通りの”上澄み”を利用したものになり、現段階では再生医療等の安全性の確保等に関する法律で規制されていないのが現状です。
「規制がない=言いたい放題やりたい放題」が出来る為、美容液や化粧品等の美容商品を中心に、表現から何から凄い事になっていますが、業界内の人間であれば当該事情を知っていたとしても、業界外の人間であれば、その事情を知らないのが普通かもしれません。
何も知らない方にとっては、規制の存在する土壌から表現されたものと、規制の存在しない土壌から表現されたものとでは、どちらが分かり易く見えるかと言えば、後者に偏ると思います。
勿論、規制が存在するから効果が保証されているとか、安全性が高いとか、何か起きた場合のフォローアップも確立されている等も決してありませんし、規制が存在しても規制外の表現をしている事例も珍しくありませんので、気を付ける必要があります。
※1)https://www.jsrm.jp/news/news-15165/
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid0u4arg59YbPrEnFqhCcBWkC7mndqs4GfJaMyPxwnijd9LLJrUSKs4hSJVrzuwswvol
https://nordot.app/1165522306382906206
>>性犯罪事件の公判に横浜市教育委員会が多数の職員を動員して一般傍聴者を閉め出した問題
久しぶりに気持ち悪いニュースを見た印象ですが、
>>公判計11回で、1回当たり最大50人を動員した
>>2019~24年度に行われた4事件の公判計11回について、市教委事務局の延べ525人に傍聴を呼びかけた※1)
性加害と一般傍聴者の邪魔、それぞれの形として表現された行為は勿論、行為までの発案の背景と性質、また、それに賛同して傍聴席を埋めた人間も含め、四捨五入で全員気持ち悪いです。
※1)https://www.yomiuri.co.jp/national/20240521-OYT1T50165/
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid05aXKfxbu8RSAxYifZ37DdFJMW7E5k413ZoufJxxU3G8FKwC4S2KFtoGSeyW5X5ffl
>>日本のリリカの申請資料概要には、GABA系への影響がないかのように記載されている。しかし、プレスクリル誌の記事で詳細にレビューされているように、臨床的に依存・乱用・中毒・離脱症状が出現することは明瞭
ベンゾを嫌いリリカを好んで処方する傾向は、特に2017年3月、PMDAのベンゾ離脱の発表以降、顕著に見られ始めていますが、リリカもベンゾと同様にGABAレセプタへの影響は避けられない為、ベンゾ離脱と類似する症状群が惹起される恐れがあり、注意が必要と感じます。
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid0HLm1VG56VXXAQd7kqQWguBRStXbpbddJxCZMZBH2GaHKc4ss8rDL2LBjrN5Ub8qbl
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f67af4a1a7d52fa01b221f28153d70f8b5d2210
>>水で洗うと鶏の表面に多く付着しているカンピロバクター等飛び散り、シンクの広範囲に広がることが分かっています。特に危険なのは生で食べる他の食材や完成した調理品に付着させることです。
>>例え鶏肉を洗わなくても、鶏肉など生の肉を調理する時にはまな板を分けたり、使用後に消毒や中性洗剤で十分洗浄する事、そして、シンクの中も中性洗剤で洗うなどの配慮が必要
>>「特に危険なのが、数十個程度という少ない細菌数でも食中毒を起こすことがあるカンピロバクター食中毒のリスクが高いといえます」と説明。「市販の生の鶏肉の半分ぐらいにカンピロバクターが付着していたという報告がありますので、生の鶏肉にはカンピロバクターが付着していると思って調理する必要があります」
>>「典型的な食中毒症状を起こしますが、まれに感染後数週間後にギラン・バレー症候群という末梢神経障害を発症することがあり、注意が必要です」
>>「食中毒菌は熱で死滅しますので、付着してても(原文ママ)調理すれば安心してお召し上がり頂けます」
-----
取り敢えず「流水で洗う」、或いは「ベジセーフ」や「ホタテパウダー」等の強アルカリ性で洗い落としたいのは(両方とも使った事はないのですが、当該商品が振りかけられた表面の脂や蛋白(野菜と農薬の関係性なら、付着しているアジュバント)を溶かし落とすってイメージで良いのかしら ちゃう?)、当該商品等が謂う農薬だけでなく、
肥育ホルモンや抗生物質、飼料に含まれる農薬の類も全て視野に入っている為かもしれませんが、これらの文言を含めるとより早急に削除対象として吊し上げられるリスクもある為、敢えて農薬だけを標的としているのか、それとも純粋に買ってきたものは野菜でも肉でも流水で洗おうという感覚かは分かりませんが、
仮に可食部位となる筋肉や脂肪、皮、或いは内臓に残存していた場合、それらが流水等で洗い落とせるかは不明なのと、仮に洗い落とせたとしても、人間が口に運ぶ時はある程度の固形の状態が維持されたままとなるので、隅々まで洗い落とす事は不可能かもしれませんし、それは根から吸い上げた野菜の類も同じ事かと思います。
それはそうと、個人的にこれからの季節で注視しているのが、より身近なセレウス菌と呼ばれるものです。カンピロバクターは中心部を75度以上で1分間以上に渡って加熱すれば防げるようですし、何らかの理由があって流水で洗うとしても、飛び散らかる洗い方をしなければ問題はありませんが、セレウス菌は熱に強く126度90分の加熱でも防げないと言われています。
こちら※1)を参考までに引用すると、
-----
原因となる食品
米・小麦・豆・野菜などの農作物・穀物を原料とする食品。例えば、「チャーハン」や「ピラフ」、「スパゲティー」や「焼きそば」などは要注意です。
菌の特徴
90℃、60分の加熱にも耐える"芽胞"を形成する。30℃前後でもっとも活発となり、冷めた調理済食品中で急激に増殖する。
"芽胞"を一度作ってしまうと、通常の加熱では死滅しません。そのため、"芽胞"ができないように、調理をするのは必要最小量にし、調理後は早めに食べきり、室温で放置せずに残りを保存する場合は速やかに冷蔵庫に保存しましょう。
主な症状
嘔吐型は激しい吐き気・嘔吐など。下痢型は腹痛・下痢など。
潜伏期間
嘔吐型は30分〜6時間。
下痢型は8〜16時間。
-----
軽い重いの幅はあるのと、その時の体調にも左右される場合はありますが、軽い場合はそもそも気が付かない、或いは何かちょっとお腹が痛いな程度で済む場合もあるようですが、重い場合は身動きが取れなくなる程、また、死亡例もあり、チャーハン病、チャーハン症候群と呼ばれる時もあります※2)。
近い年で有名なものは2023年、駅弁に入れるご飯の温度管理が悪かった事がひとつの原因と考えられた、大規模な食中毒もありましたが、こちらもセレウス菌(と黄色ブドウ球菌)が検出されていました※3)。それから間もなくのデスマフィンも当該菌の可能性が挙げられていました※4)。
「時間が経った食べ物でも再加熱すれば大丈夫」「レンジで熱くすれば大丈夫」という話を聞く時もありますが、全ての菌が熱に弱い訳ではない事、また、もしかしたら鶏肉以上に身近に口に運ぶ穀物類でも命を脅かす菌が存在する事、室内での放置も今までの涼しかった季節と今は違う事、室温次第では違う事も踏まえた上で、
諸々の面倒臭さを無くしたい場合は、自分で作ったものなら調理内容や食べる迄の時間も大概は把握出来ていると思うので、さっさと食べる、他人が作ったもので調理内容や出来上がりから経過した時間、或いはその時間経過の間、保存状態を把握出来ない場合は食べない、これで回避出来ます。
まとめると、ベジセーフ含む類似商品は、何でも洗えるが一般的なスタンスかと思います。先述通り強アルカリ性で、表面の脂や蛋白質の溶解に優れている為、食べ物から家具や壁、床等、幅広い用途があるのでしょう。食中毒の問題は新鮮で清潔なものを直ぐに食べれば回避出来る、左記に当て嵌まらず不安があるなら食べない、程度で大丈夫ではないでしょうか。
※1)https://family.saraya.com/kansen/sereusu/
※2)https://nishinomiya-naishikyo.com/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%81%A7%E9%A3%9F%E4%B8%AD%E6%AF%92%EF%BC%9F%E3%80%8C%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF/#:~:text=%E3%80%8C%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E3%81%AA,%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
※3)https://www.yomiuri.co.jp/national/20230923-OYT1T50231/
※4)https://mainichi.jp/premier/health/articles/20231215/med/00m/100/002000c
参考)https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/427-cereus-intro.html
https://www.facebook.com/kouta.fujiwara1/posts/pfbid035enHXtWz9cQ3e23FT3By3gpgjayTLZiXjhPXf36JsnSsGTp67Ej4guFrJZoYF5Wal
「知れば知るほど使いたくない」は、薬物に限らず様々な場面で聞く話ですが、その多くは使用後に生まれる所感であって、知らない時ほど、或いは知らないからこそ「使いたい」という感情は高いのではないでしょうか。
脊椎外科医100人に「あなたも腰を傷めたら、患者に施している手術を自身も受けたいか」と聞いたら、手を挙げたのは1人だけ等、知っているほど「保存療法で何とかならん?」となりがちで、知らないタイミングから薬物の使用後にこの所感が生まれた時は、既に一定のダメージ、或いは既に死亡というジレンマがあります。
また、「使いたくない」というネガティブな所感を想起する暇も与えないのが、〇〇病や〇〇障害、〇〇症候群等の傷病名であり、合法薬物による弊害が惹起された際の処方した側の逃げどころです。これが類似した作用機序を持つ違法薬物であれば、全く異なる対応になると思います。
「効く」「効かない」の対極論であれば、「効く」と思います。痛いのも分からなくなるかもしれませんし、上がったものは下がり、下がったものは上がるかもしれません。立ち位置的に「薬を飲んでも効かないから来た」は珍しくないものの、「効く」話もしっかりと拾い上げています。
ただ、この論点は「効く」「効かない」であって、「治る」「治らない」ではないので、履き違えると追々大変で面倒な事になりがちですが、肌感覚としても会話の節々から感じる「治る」「治らない」で服薬している雰囲気が多いのは、
どこかで誤った表現を伝えられている可能性があるからで(※例 あ~〇〇さん、この薬を飲んどきゃ‘’治る”よ)、その伝達内容が患者教育とするならば、単に嘘を付かれているか、知らないだけか、教育した人間もそのように教育されてきただけの可能性etc…です。
折角なので付け足すと、「この薬物を飲むと死亡確率が上昇します」と、本人なりの誠意を込め、処方している医師も居ますが、そのように伝えると2度目の来院はないようで、正直な話を真に受けず、別な所で同じ薬物、或いは同じ系統の薬物を貰う事例も珍しくないようです。
正直に伝えれば来なくなり、嘘を付けば死ぬまで飲み続ける、嘘という言葉は強いものの、その他に思い浮かぶ言葉は隠ぺい程度なのでこのまま続けますが、薬物の弊害も病気にして成り立つ世界は、延々と嘘を付き続ける息苦しさがあり、そのストレスが関連してか、特に精神科医の自殺は一般人の5倍というデータもあります。
薬物使用の背景の多くは、「具合が悪い」も平行していると思いますが、人間は具合が悪いと視野は狭く、冷静さが失われがちになるものの、既に「知れば知るほど使いたくない」という人間も、実体験を通して数多く存在している現実も併せて予習した上で、何かあった場合は検討するのも良いのかもしれません。
----------
クリックまたはタップでご覧頂けます ⇒【治療費/所在地/自己紹介】 ⇒【フェイスブック】
【電話】 0173-74-9045 (携帯電話 090-3983-1921)
【診療時間】 7:00 ~ 21:00 ※時間外対応可
【休診日】 なし 土曜/日曜/祝祭日も診療しています
【メール】 fujiwaranohari@tbz.t-com.ne.jp
ご予約/適応症状/非適応症状/病態解釈/経過予測/リスク/費用/治療内容などのご相談やご案内はメールでも承っています。お気軽にご連絡下さい。
----------